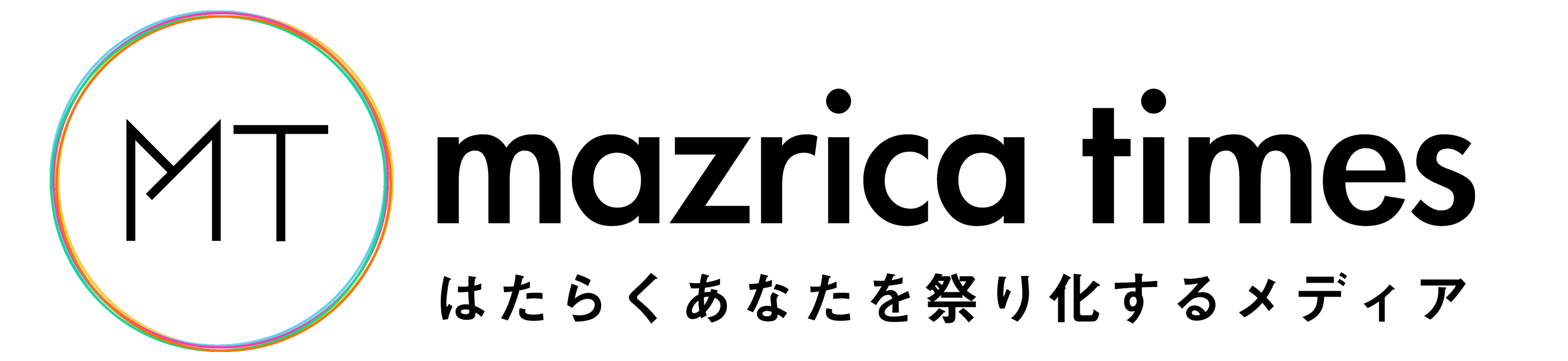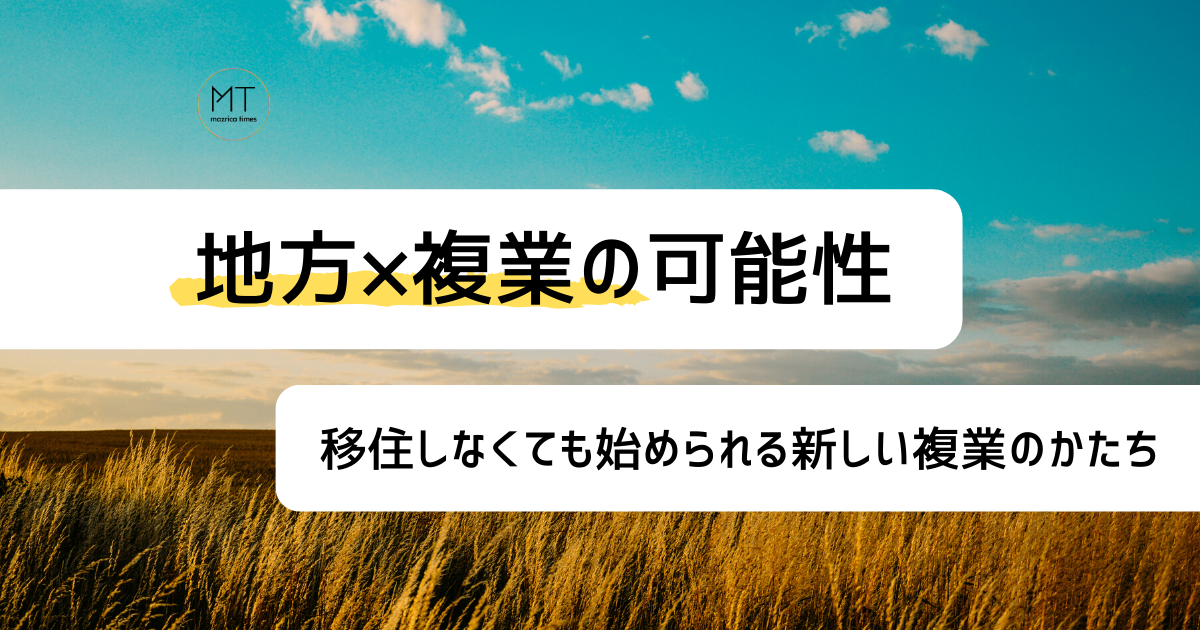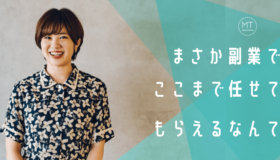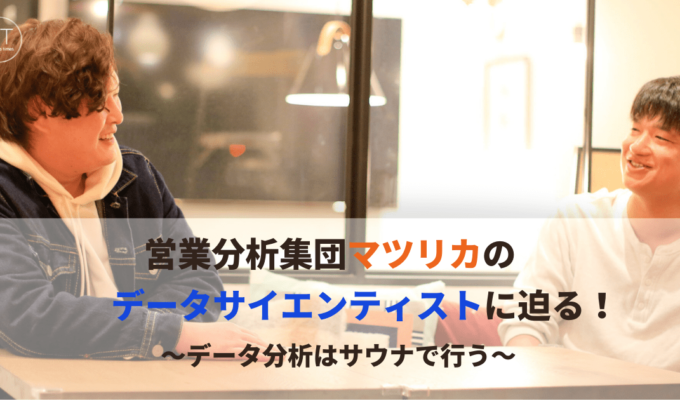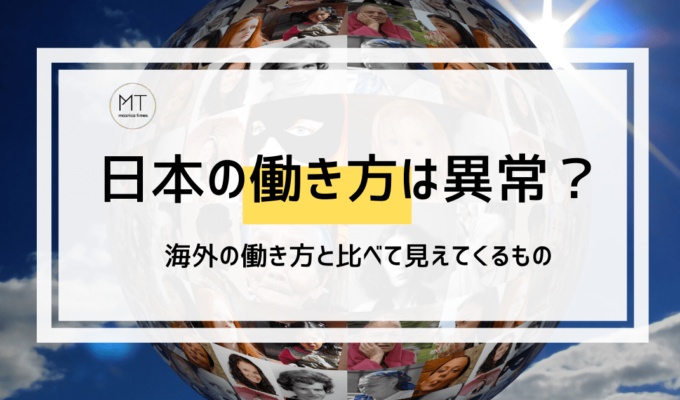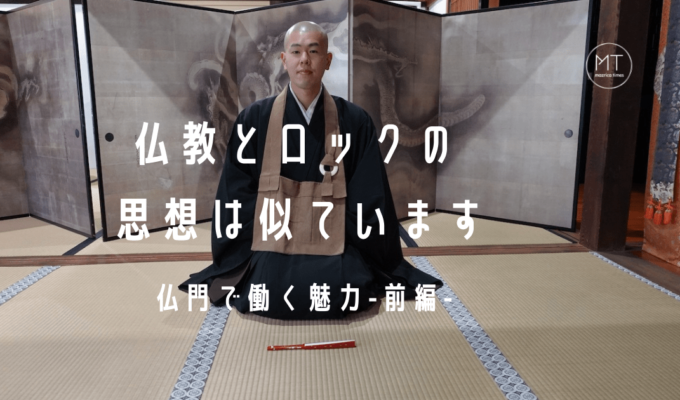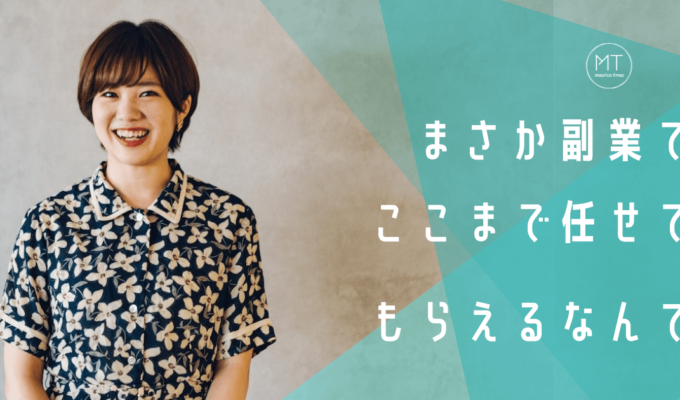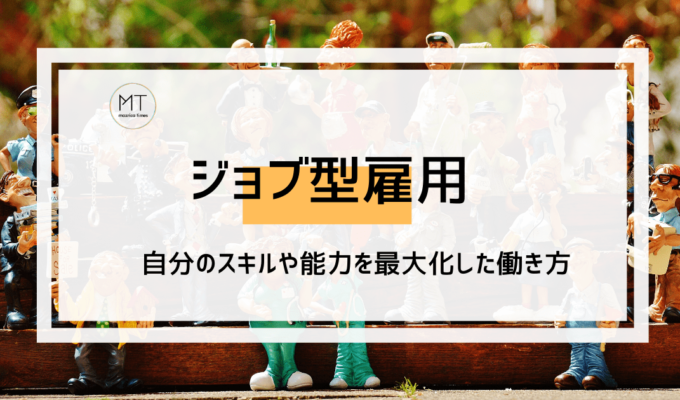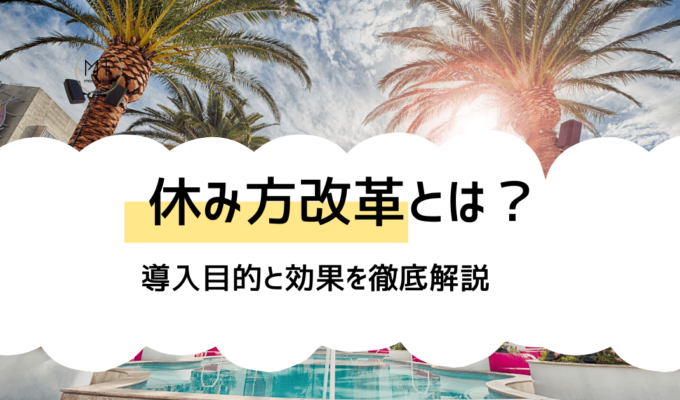働き方改革により、リモートワーク、時差出勤、ワーケーションなどさまざまな働き方が生まれています。ここ数年、特に盛り上がりを見せているのが複業です。さらに、人手不足という地方の課題を複業人材が解決できるのではと、今「地方複業」という切り口で民間企業や自治体が注目しています。この記事では、地方複業の可能性について迫ります。
目次
複業・副業を含むフリーランスの経済規模は23.8兆円
フリーランス、特に複業市場はここ数年で急速に拡大しています。ランサーズが行った調査『新・フリーランス実態調査 2021-2022年版』によれば、複業・副業を含むフリーランスの経済規模は推定23.8兆円に達し、全体のフリーランス人口は日本全体の約20%にあたる約1577万人という結果が出ています。
複業が注目される背景には、以下の3つが理由として挙げられます。
- 働き方改革法案の成立
- 老後資金2000万円問題
- 終身雇用制度の終焉
日本のあり方は「集団」から「個」へと大きく変化しました。今までは、終身雇用、年功序列が原則、大手企業に入ることで安泰が約束される時代でした。従業員同士の絆も深く、公私ともに交流のある古き良きコミュニケーションがそこにはありました。
しかし、経済が低迷し、会社は個に「生活の安定」を任せ、従業員は自分の生活を自分で考える必要に迫られています。トヨタの「終身雇用制度を守るのは難しい」という発言に象徴されるように、今まで会社という組織で同質化していた個が、いよいよ個としての力やスキルが問われ、それぞれ個人の力で勝負しなければならない局面に来ています。
地方複業が注目されている?そのワケとは?
地方複業とは?
地方複業とは、「都内にいる複業人材が地方に出張あるいは短期滞在 or 長期滞在し、地場産業の担い手として、業務を遂行する働き方」を指します。なぜ地方複業が注目されているのでしょうか?
深刻な中核人材の不足
人手不足は地方に限らず、日本全体の深刻な課題とされています。三菱UFJリサーチ&コンサルティングが2018年に行った調査によれば、2023年までは労働力の人口増加が続くものの、2023年から減少のペースが早くなり、2029年にはリーマン・ショック直後に匹敵する水準までに下落すると予想されています。
参考:2030 年までの労働力人口・労働投入量の予測~人数×時間で見た労働投入量は 2023 年から減少加速 〜
東京には人が集まるため、当面は大きなダメージは少ないかもしれません。しかし、地方の中小企業は、後継者問題や経営者の高齢化により、人材確保が喫緊の課題となっています。東京一極集中の状態になっている以上、個々の企業努力ではなかなか解決しない問題です。そこで地方複業という形で、都心部の複業人材でリソースを補い、解消できるのではと期待されています。
関連記事:継業(けいぎょう)とは|移住者が事業のバトンを受け継ぎ、地方に新たな価値を生み出す
新しい情報やトレンドの伝達
新しい情報やトレンドは、人が多く集まる都心部に集中します。都心部から物理的に離れているほど情報の伝達は遅くなります。VUCA(ブーカ)と呼ばれる不安定で変化の激しい時代だからこそ、トレンドを追うことやユーザーのニーズを把握することを課題としている地方企業も多いです。都心部の人に関わってもらうことで、複業人材が都心部と地方のハブとしての存在を果たすことができます。
関連記事:VUCA(ブーカ)の意味とは?|激変する時代を生き抜く組織のあり方・働き方
魅力の再発見
地方に住む人からすると、「当たり前」「特徴とはいえない」と思うモノやコトも、都心部の人から見ると、魅力に感じることも多くあります。こういった、「ヨソモノ」の視点を入れることで、魅力を再発見でき、地域全体の活性につなげることができます。
地方複業に欠かせないキーワード
関係人口とは?
地方複業をするうえで押さえておきたいキーワードが「関係人口」です。関係人口とは、観光を目的に訪れた「交流人口」とは異なり、滞在中に地域、地域の人と関わる人材を指します。
地方では、若者の流出や労働者不足という課題を抱えています。インバウンドという観点で、人を呼び込めば、短期的には地域活性につながりますが、地域に人が定着するサイクルは生み出せません。これらの観点から、地域に深く関わり課題を解決する関係人口に注目が集まっています。政府もこの動きに注目し、2018年に関係人口を創出する「関係人口創出・拡大事業」を実施しています。
関連記事:移住でも観光でもない、ゆるく関わる「関係人口」|地方創生のカギとなる概念
今注目されているワーケーションって?
地方複業に関連するワードとして注目されているのが、「ワーケーション」です。ワーケーションは、ワーク(働く)とバケーション(休暇)をかけ合わせた造語で、アメリカで生まれた働き方です。もともとは、有給休暇の取得率アップのために普及しましたが、関係人口を増やすために、地方自治体や民間企業が採用しているケースも増えています。
関連記事:旅行しながら働く「ワーケーション」という働き方。バカンスと仕事の両立はできる?
地方複業のメリット
多面的な視点を養える
複業のメリットにも重なる部分ですが、特に地方複業では新しい仕事だけでなく、新しい地域という観点が加わります。異なる文化を持つ、馴染みのない土地に足を運ぶことで、新たな気付きや刺激を受けることができます。
場所の依存からの解放
定期的に地方へ訪れることで、今の居住地域に固執せず、他の場所でも仕事ができる実感を得られます。週末だけ地方複業をして、地方に魅力を感じ、そのまま定住したケースも多くあります。
関連記事:アドレスホッパーという”定住しない暮らし方”|住所や税金はどうするの?
課題を発見・提案する力を磨ける
都心部の仕事と異なり、地方の仕事は課題を発見・整理するところから始まります。また、地方企業は、1人社長や家族で経営しているケースが多く、業務の切り出し方から考えていく必要があります。「一緒に仕事を作っていく」という点で、課題発見力や提案力が磨かれます。
地方複業をすすめる上での注意点
地方複業を始める前のイメージと現実はやはり違うもの。思わぬアクシデントにみまわれないよう、気をつけたい注意点について知っておきましょう。
満足のいく報酬がもらえるとは限らない
特に、居住地域や勤務している地域と離れている縁もない場所なら、まずは関係づくりが必要です。すぐに満足のいく報酬がもらえるとは限りません。報酬を目的にしていると、モチベーションが保てなくなります。この地域に関わりたい、課題を解決したいという想いを持てるかが大切です。
「仕事を作り出す」のが仕事
地方には課題が山積していますが、地方企業がその課題を自覚していない、整理できていないことも多いです。そのため、地方に行けば自動的に仕事がもらえるわけではありません。関わり話を聞き、課題を引き出して「仕事を形にする」フェーズから仕事が始まります。
仲介者の存在が必要
地方複業では、その土地に居住する仲介者(キーマン)の存在が欠かせません。都市部の正社員と地域企業を結ぶ副業プラットフォーム「Skill Shift」、株式会社トレジャーフットが運営する「GOING GOING LOCAL」、岩手県が運営する「遠恋複業課」など、地方自治体、民間企業問わず、地方と複業人材をつなぐマッチングサービスも急速に立ち上がっているので、こういったプラットフォームを活用すれば、よりスムーズに地方複業にチャレンジできます。
地方×複業にはさまざまな形がある
地方×複業と聞くと、移動コストや労力を考えて、最初の一歩を踏み出せない人も多いと思います。しかし、地方複業の形は千差万別で、自分にあった働き方をやりながら作ることも可能ですここでは、働き方の異なる3つの事例をご紹介します。
会社員(フルリモート)×地方移住で複業
「ソニックガーデン」でエンジニアをしている中谷さんは、瀬戸に移住し東京の業務を全てフルリモートで行っています。打ち合わせも全てオンラインで済ませるため、お客さんとは最初から納品まで顔を合わせることはありません。瀬戸では、複業として2018年11月から子どもたち向けのプログラミング道場『CoderDojo瀬戸』を開催しています。
関連記事:瀬戸に移住しリモートワーク! プログラミング指導で地域交流を広げる会社員
二拠点居住で地方複業
辻さんは、トレジャーフットというベンチャー企業に勤務しながらも、フルリモートで東京と地元である山梨の里帰り二拠点生活を送っています。山梨では、複業活動としてデリ(サンドイッチや持ち帰り用の惣菜を販売する飲食店)を開く計画に向けて動いているそうです。
関連記事:なぜ二拠点生活をはじめた?東京と山梨を行き来する辻さんが語る、移動しながら過ごすくらし方の魅力
月数回だけ地方に関わり複業
旅行系ベンチャー企業に勤務する小林さんは、月に2〜3日のペースで、熱海のホテル「ニューアカオ」の「アカオハーブ&ローズガーデン」でプランナーとして複業勤務しています。もともとは週末複業スタイルをとっていましたが、より複業に専念できるよう、本業を週5勤務から週4勤務に切り変えています。
関連記事:会社員だからこそ感じた“危機感”からの脱出。自分のキャリアをつくる「地方×複業」という選択
まとめ
今や複業ブーム、複業に興味を持つ人が急速に増えているように思います。やりがいやスキルアップで始める人もいれば、収入アップのために複業を始める人もいます。こと、地方複業に関しては「報酬」第一で考えないようにしましょう。さきほども書きましたが、地方に行けば自動的に仕事がもらえるわけではありません。話を聞き、課題を引き出し、提案する。主体的に地方に関わることが大切です。