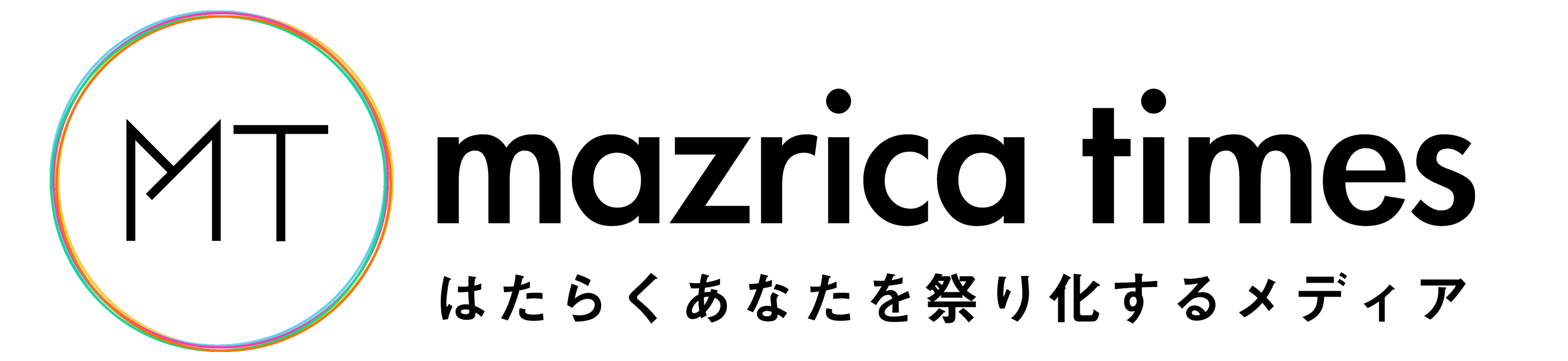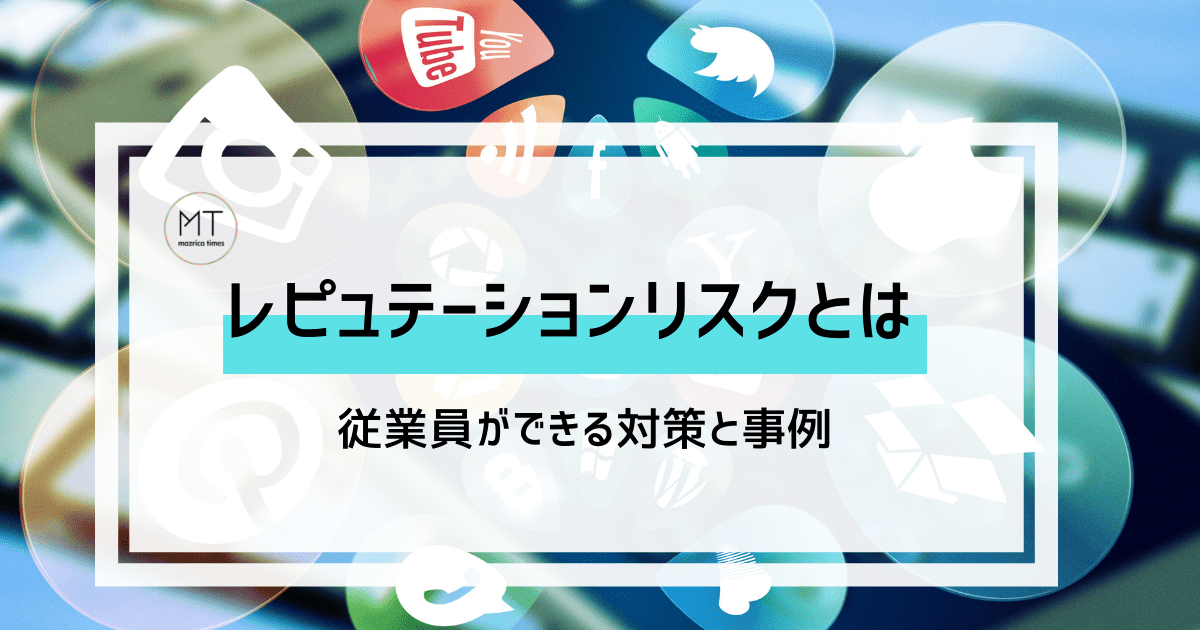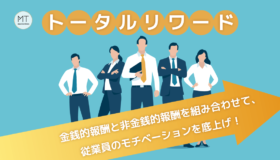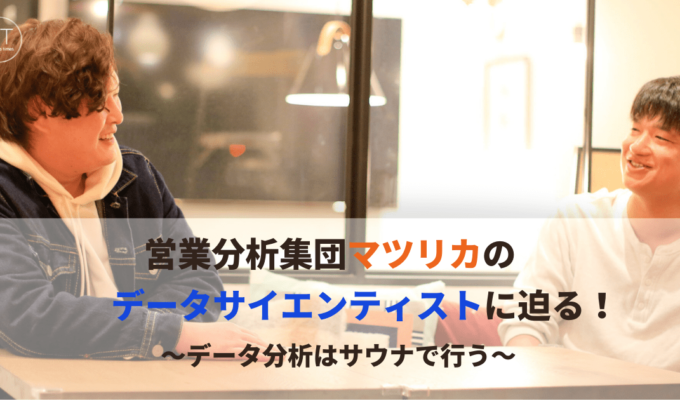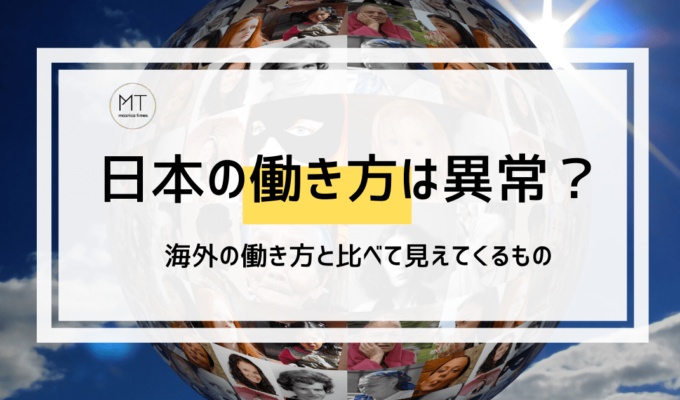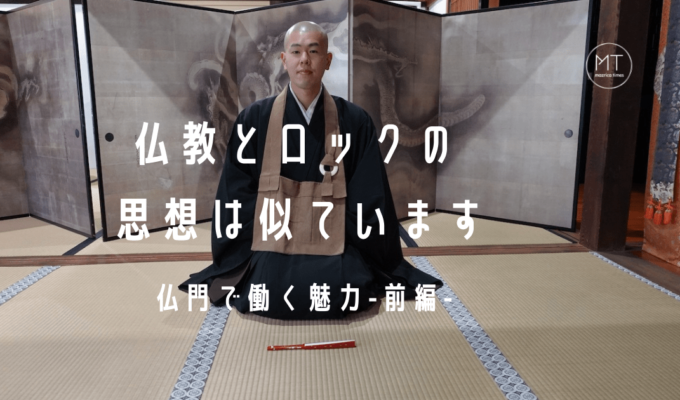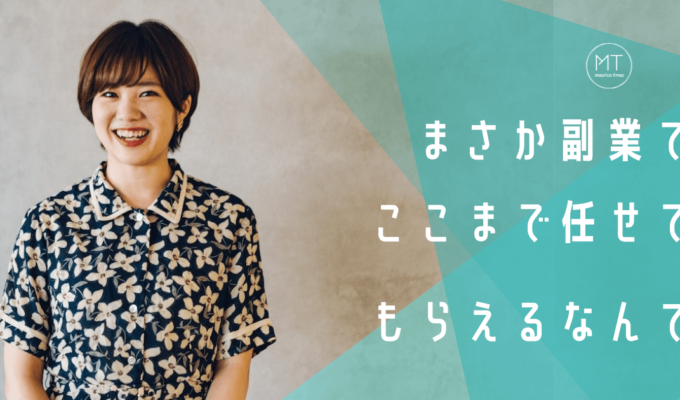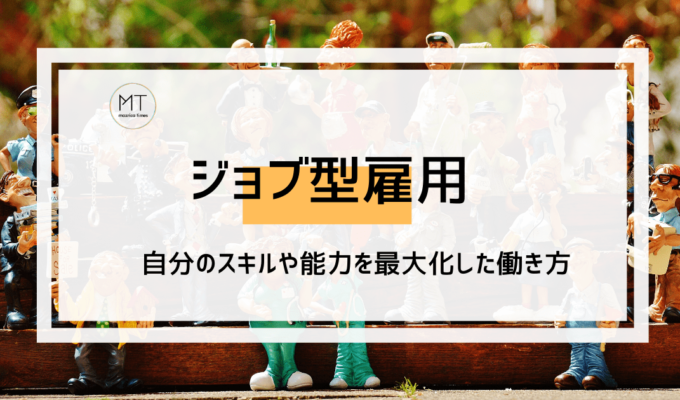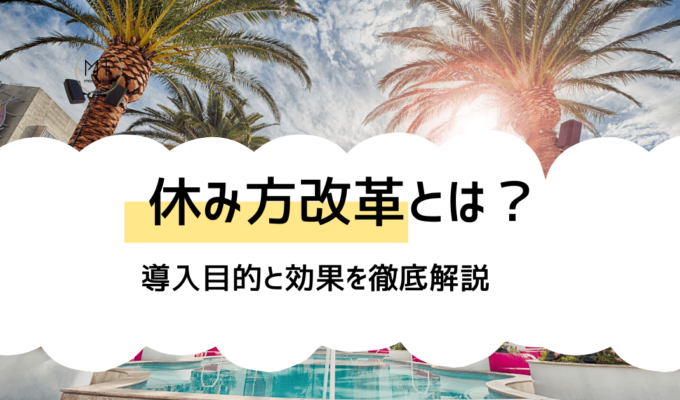誰でも、SNSやYouTubeなどで簡単に発信できるようになったことで、誹謗中傷や風評被害のリスクが高くなっています。会社に対するマイナスの評価や評判が広まり、事業活動に悪影響を及ぼすリスクを「レピュテーションリスク」と呼び、事業戦略の一環として検討する会社も増えてきています。本日は、従業員の方も考えたいレピュテーションリスクについて解説いたします。
目次
レピュテーションリスクの意味とは?
レピュテーションリスクとは、会社に対するマイナスな評価や評判が広がることで会社の信用やブランドを毀損するリスクを意味します。従来においても、知人や友人間における口コミや噂によって、会社やお店の評判は広まっていたため、口コミに対して一定の対策や注意を払う必要がありました。
しかし、近年はSNS、ブログ、YouTubeなど、不特定多数の目に触れるインターネット上で情報発信ができるようになったことで、情報拡散の速度が上がりました。
このような状況下では、ほんの些細な行動一つが火種となり、炎上を引き起こしてしまいます。そのためには、会社は今まで以上にコンプライアンスの遵守、モラルやネットリテラシー教育などを実施していくことが求められるでしょう。
なぜ、レピュテーションリスクが重要なのか?
では、なぜレピュテーションリスクが事業活動において重要視されるようになったのでしょうか。そこには大きく2つの要因があります。
まず1つ目が、情報伝達手段の変化です。従来は、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、Webメディアなどを通じて情報が伝達されていました。食べログやアットコスメ、AmazonといったWebサイトでは、口コミをチェックすることができますが、即時性は高くありませんでした。
それと比較して、SNSではついさっき起こった出来事をそのままダイレクトに発信できます。さらに、リツイートやリポストと呼ばれる機能を使えば、数日程度でたやすく数万人、数十万人に届けることができてしまいます。
もう1つが、評価基準の多様化です。事業活動において価値の高い指標は売上ですが、近年はESG投資という言葉もあるように、コンプライアンスや、環境配慮、多様な人材の活躍など、複数の指標で評価がされつつあります。
多様な価値観や指標があることを理解せずに発言や行動をしてしまうと、一部の人からは非常識、道徳がないと受け取られ、炎上するということになりかねません。
関連記事:共創社会で重要視される戦略|SX(サステナビリティトランスフォーメーション)とは?
レピュテーションリスクによって起こること
レピュテーションリスクによって、どのような問題が起こるのでしょうか。
プランドイメージの毀損
マイナスな評価や評判が広がることで、今まで積み上げてきたブランドイメージが毀損します。ブランドイメージは、取引継続や資金調達などの判断にも大きな影響を及ぼすため、長期化した場合は、業績の悪化を招きます。
業績の悪化
レピュテーションリスクによって、業績の悪化をもたらします。特に、火種となった出来事が重大な過失であった場合、ネガティブなコメントや口コミなどで溢れかえり、注文数の低下だけでなく返品や返金を求められることもあります。
優秀な人材の確保が難しくなる
ひとたび悪い噂がたってしまうと、それがたとえ虚偽の情報であったとしても、イメージの回復は難しくなります。それは、顧客だけでなく求職者においても同様です。優秀な人材の確保が難しくなってしまう可能性が高まります。
レピュテーションリスクの発生要因と実際の事例
ここでは、レピュテーションリスクの発生要因と実際の事例について、いくつか紹介していきます。
従業員の不正・不祥事
まず、レピュテーションリスクが発生する原因として考えられるのが、従業員の不正・不祥事です。「酒に酔って知らない人を殴ってしまった」、「有名人や芸能人の来店情報など、仕事でしか知り得ない情報を無断でSNSにアップした」などが挙げられます。たとえ、過失が従業員にあったとしても、責任を問われるのは管理者、雇用主となるため、迅速な対応が必要でしょう。
消費者からの口コミ・評判
「店員の接客態度が最悪だった」、「購入した商品が壊れていたのに返品に応じてくれなかった」といった消費者からの口コミや評判です。迅速にかつ誠実に対応しないと、最悪の場合、SNSで拡散されて炎上してしまうことも。
関係者からの内部告発
脱税やパワハラ、産地偽装といった不正行為や悪質な行為を、従業員やOB・OGによって告発されてしまうケースです。内部告発が行われる場合、すでに事態は深刻化しているものと想定されます。テレビや新聞などのマスメディアで明るみになった場合、会社のブランドイメージを大きく毀損することになるでしょう。
風評被害
根拠のない噂や間違った情報も、SNSなどで多くの人に拡散されれば、それが事実として世の中に浸透してしまうことも。情報が広まると、誤解を解いて信頼を回復させるのには多大な時間を要します。風評被害が原因で、会社を廃業せざるを得なくなった、お店を畳んだといった事例も少なくありません。間違った情報を拡散した者は、偽計業務妨害罪や名誉毀損罪として立件される恐れがあります。さらに、虚偽情報と知らずにリツイートやシェアをした場合も罪に問われる恐れがあります。十分注意しましょう。
レピュテーションリスクを回避するポイント
では、未然にレピュテーションリスクを回避するには、どのようなポイントを押さえておけば良いのでしょうか。
迅速に対応する
レピュテーションリスクを未然に防ぐために重要なポイントがスピードです。シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所の調査によれば、SNSなどで炎上した事例が記事化、テレビで放送されるまでの期間でもっとも多かったのが「24時間以内」で48.0%となりました。
つまり、初動が遅れてしまうと、次々と他のメディアや媒体に転載されていき、収集がつかなくなる恐れがあるということです。万が一拡散されている情報に誤りがあったとしても、放置せず誠実に対応しましょう。
誤解を招かないよう、正確な情報発信につとめる
情報発信をすることは非常に大切ですが、よく見せようとしたり、事実と異なることを発信したりしてしまうと、クレームやトラブルの原因となります。また、価値観や意見がわかれるような政治・宗教・人種などに関わる発信は控えましょう。価値観は多様になり、OKとNGの線引きはより曖昧になっています。誰が読んでも不快にならないという視点で、発信することを心がけましょう。
あらゆるステークホルダーに対して真摯に向き合う
あらゆるステークホルダーというのは、顧客や取引先、投資家に限りません。自宅の近隣に住む人々、よく行くコンビニやカフェの店員さん、家族、地球環境など、自分が生きるうえで関わるものすべての人です。
「一億総発信時代」と呼ばれる昨今だからこそ、「不機嫌だから、つい店員さんに八つ当たりをした」「知人同士で、少額の違法賭博をした」というささいな行動が、何かの拍子に明るみとなり、炎上に発展することを肝に銘じておかないといけません。
終わりに
レピュテーションリスクは、会社だけでなく、そこに所属する従業員も考えないといけない問題です。炎上が起こってしまうと、できる対処は限られます。公私ともに、日頃の言動や態度が誠実で真摯なものになっているか、今一度見直してみましょう。
この記事を書いたひと

俵谷 龍佑 Ryusuke Tawaraya
1988年東京都出身。ライティングオフィス「FUNNARY」代表。大手広告代理店で広告運用業務に従事後、フリーランスとして独立。人事・採用・地方創生のカテゴリを中心に、BtoBメディアのコンテンツ執筆・編集を多数担当。わかりやすさ、SEO、情報網羅性の3つで、バランスのとれたライティングが好評。執筆実績:愛媛県、楽天株式会社、ランサーズ株式会社等